| 土曜は、午後、恒例の「零戦についての深い話 12」を聴きに神田まで出掛ける。 神田駅前商店街で、いつものようステーキ重で昼食。 |
 |
| 今回のお題は、零戦52型について。BUNさんの話は、よくある定説覆し。資料に基づき、誤解を解きほぐしていくのは毎度ながら面白い。 |
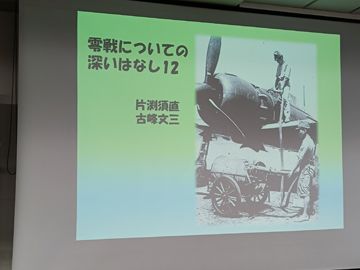 |
| 片さんの話は、今回はキングタイガーの塗色について――映画はまだまだ完成しないようだ。 |
 |
| あと、中村さんの回収部品の話、宮崎さんも52型の話、坂井田さんは緑十字機についてで、今回もそれぞれこだわりの内容だった。 終わった後、横浜に戻って、駅前に新しく出来た焼き肉屋でがっつり……さすがに食い過ぎて、帰路、途中で動けなくなるほどだった。 次は来年8月。 |
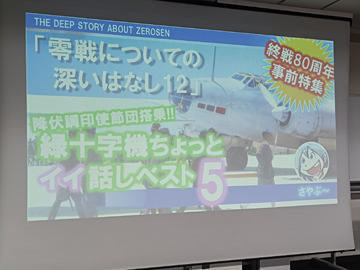 |
